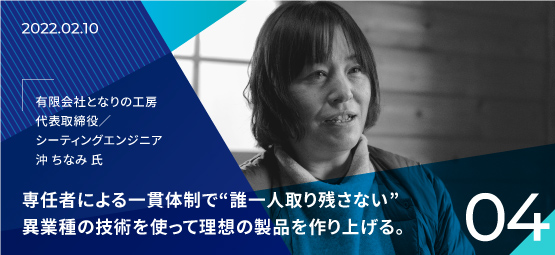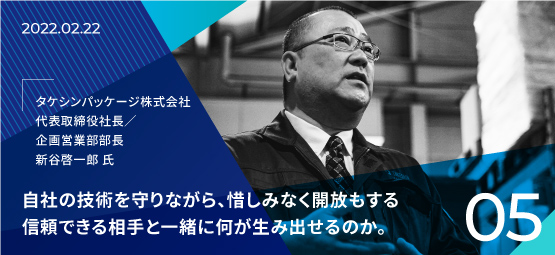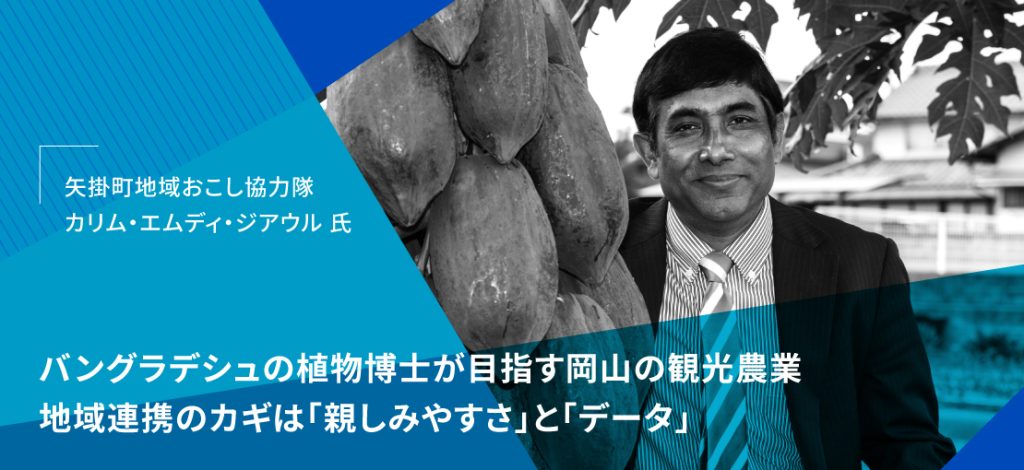INTRODUCTION
of corporate cases and initiatives
PICK UP 取り組み事例紹介
WAKABAYASHI MIKI
アトツギ女性経営者が描く倉敷のこれから
会社の歴史と事業の軸 ― 「その時代に必要とされることを」
簡単に御社のご紹介をお願いします。
株式会社若林平三郎商店は文久元年(1861年)創業で、来年で165年を迎えます。倉敷の土地に根ざし、商いを続けてきました。今は主に“運輸業”“不動産業”“飲食業”の3つの柱で事業を展開していますが、共通しているのは“地域の暮らしやまちを支える事業”であることです。
これまで代々の経営者が、その時代に必要とされるものを見極め、事業の形を変えてきました。たとえば醤油の醸造業から卸売へ転じたのは、曽祖父が『これからはナショナルブランドの時代になる』と考えたから。新聞に関西工場新設のニュースが出たのを見てすぐに、大手調味料メーカーの本社に出向き特約店にしてほしいと直談判し、販売を始めたんです。その後、地域のニーズに応えて様々な事業へと展開し、現在の形になりました。
“続けるのか、形を変えるのか”を常に決断しながら歩んできたのが、株式会社若林平三郎商店の歴史です。
これまで代々の経営者が、その時代に必要とされるものを見極め、事業の形を変えてきました。たとえば醤油の醸造業から卸売へ転じたのは、曽祖父が『これからはナショナルブランドの時代になる』と考えたから。新聞に関西工場新設のニュースが出たのを見てすぐに、大手調味料メーカーの本社に出向き特約店にしてほしいと直談判し、販売を始めたんです。その後、地域のニーズに応えて様々な事業へと展開し、現在の形になりました。
“続けるのか、形を変えるのか”を常に決断しながら歩んできたのが、株式会社若林平三郎商店の歴史です。

2030年問題を見据えた運輸事業改革
代表就任後、最優先に取り組まれていることは何ですか?
去年8月に社長に就任してから、最初の1年は運輸事業に力を注ぎました。トラック新法も令和7年度から本格的に適用範囲が広がり、既に一部の規制は段階的に施行されています。労働時間の上限規制など、業界全体で働き方の見直しが求められる中、コンプライアンスを遵守できない会社は当然運営が難しくなっていくと考えております。さらに“2030年問題”は物流業界にも影響が大きく、日本中の荷物の3分の1が運べなくなるという危機も迫っています。
その中で弊社としては、労務環境を整え、安全性と品質を高め、運送会社としてのレベルアップを進めています。運輸業の価値を再認識してもらえる土壌をつくりたいと思っています。
『正しく伝えることが誠実さ』だと思うので、社員や取引先とも対話を大事にしながら改革を進めています。
その中で弊社としては、労務環境を整え、安全性と品質を高め、運送会社としてのレベルアップを進めています。運輸業の価値を再認識してもらえる土壌をつくりたいと思っています。
『正しく伝えることが誠実さ』だと思うので、社員や取引先とも対話を大事にしながら改革を進めています。

承継のきっかけと前職で培った営業力
アトツギを志したきっかけは何ですか?また、前職の経験は今にどう活きていますか?
実は、幼少期から“将来は会社を継ぎたい”と考えていました。当時、会社を経営していた祖父母と父がとてもかっこよかったんです。祖母は専務として会社を仕切り、“商売って面白いよ”と毎日のように話してくれていました。その姿を間近で見て、自然と経営者を目指すようになりました。
大学ではビジネスを学ぶために県外に移り、その後、金融機関に就職しました。金融機関を選んだのは、「営業で“売る力”を身につけたい」と思ったからです。常に事業の形を変え続ける当社ですが、どんな事業でもお金を払ってくださるお客様がいてこそなので、営業の経験は今に活きています。
その後も県外で経験を積んでいましたが、父母から『帰ってくるなら時期の目処を教えて』と言われたタイミングでちょうど結婚し、夫と一緒に帰郷しました。今は、夫が経理や総務を担ってくれています。
大学ではビジネスを学ぶために県外に移り、その後、金融機関に就職しました。金融機関を選んだのは、「営業で“売る力”を身につけたい」と思ったからです。常に事業の形を変え続ける当社ですが、どんな事業でもお金を払ってくださるお客様がいてこそなので、営業の経験は今に活きています。
その後も県外で経験を積んでいましたが、父母から『帰ってくるなら時期の目処を教えて』と言われたタイミングでちょうど結婚し、夫と一緒に帰郷しました。今は、夫が経理や総務を担ってくれています。
女性経営者としての視点
“女性”であることが経営に影響した場面はありましたか?
正直、大きく痛感したことはありません。強いて言えば、女性をテーマにしたイベント等で登壇の機会をいただけることがあります。社会全体がジェンダーのバランスを意識する流れにあるので、チャンスが広がっている面もあると思います。“女性だから”と躊躇する必要はないと思います。
一方で、結婚や出産で制約が生じる現実はあります。私は、夫が家事や育児の多くを担ってくれているからこそ、経営に専念できています。男女問わず、家庭・仕事に関わる選択肢がもっと自由に認められる社会になればいいと感じています。
一方で、結婚や出産で制約が生じる現実はあります。私は、夫が家事や育児の多くを担ってくれているからこそ、経営に専念できています。男女問わず、家庭・仕事に関わる選択肢がもっと自由に認められる社会になればいいと感じています。
社員と向き合うリーダーシップ
組織を牽引するうえで大切にしていることは?
私の父(若林毅:取締役会長)は強いリーダーシップを発揮する経営者で、とても尊敬しているところです。でも私が同じやり方をやってみても、あまりうまくいきませんでした。
現場の声を聞き、教えてもらったことはできるだけすぐ改善に動こうと思っていて、聞いたり感じたりした課題は、“翌日までには、1つは解決しよう”と意識していました。
また、私は現場のことをまだまだ知らないからこそ、社員に“教えて!教えて!”と素直に聞くようにしています。そうすると社員も自然と本音を話してくれて、改善につながる課題が見えてきます。皆に力を借りながら誰よりも動くことが、現時点での私のリーダーシップの形だと思っています。まだまだ経営者としての能力も経験も足りない私は“一対一の対話”を大切にしていて、社員が何を考えているのか、どこを目指したいのか、不満も含めて全部聞くところから始めています。
現場の声を聞き、教えてもらったことはできるだけすぐ改善に動こうと思っていて、聞いたり感じたりした課題は、“翌日までには、1つは解決しよう”と意識していました。
また、私は現場のことをまだまだ知らないからこそ、社員に“教えて!教えて!”と素直に聞くようにしています。そうすると社員も自然と本音を話してくれて、改善につながる課題が見えてきます。皆に力を借りながら誰よりも動くことが、現時点での私のリーダーシップの形だと思っています。まだまだ経営者としての能力も経験も足りない私は“一対一の対話”を大切にしていて、社員が何を考えているのか、どこを目指したいのか、不満も含めて全部聞くところから始めています。
モチベーションと労働環境改革
失敗や挫折はありましたか?またどう乗り越えてきましたか?
挫折というより、後から“もっと早く気づけば良かった”と思うことはあります。辞めてしまった社員に対して、“もっと早く会社の体制を整えられていたら⋯”と悔やむこともあります。
それでもモチベーションを保てているのは、“社員の人生を良くしたい”という想いがあるからです。勤続年数が長い社員も多く、皆がここで働いたことで生活が豊かになったと思える会社にしたいと思っています。
実際に給与を過去最大の幅で引き上げたり、有給休暇の取得率を改善したり、飲食事業では労働日数を減らして休みを増やしたり、と社員一人ひとりの時間や環境を少しずつ整えてきました。単に“年商を何倍にしたい”などではなく、会社が実績を伸ばすことで、社員の給与や環境を整え、皆が豊かになることを目指しています。
それでもモチベーションを保てているのは、“社員の人生を良くしたい”という想いがあるからです。勤続年数が長い社員も多く、皆がここで働いたことで生活が豊かになったと思える会社にしたいと思っています。
実際に給与を過去最大の幅で引き上げたり、有給休暇の取得率を改善したり、飲食事業では労働日数を減らして休みを増やしたり、と社員一人ひとりの時間や環境を少しずつ整えてきました。単に“年商を何倍にしたい”などではなく、会社が実績を伸ばすことで、社員の給与や環境を整え、皆が豊かになることを目指しています。

これからの挑戦 ― 「地域への想いと夢」
今後挑戦したいことや夢は何ですか?
チャレンジしたいのは、飲食業や不動産業、運輸業といった“手段”を使って、事業に“あらたな色をつけていくこと”です。
もっとまちに近づきたいし、まちの人の顔が見えるような事業を展開していきたいと思っています。例えば、運輸事業では酒蔵や醤油蔵のようなクラフト産業を支える物流の仕組みを作ることもできると思っていますし、不動産事業でもまちのハブになるような使い方を模索しています。
2026年からの3年間で、その土台をつくっていこうと思っています。
もっとまちに近づきたいし、まちの人の顔が見えるような事業を展開していきたいと思っています。例えば、運輸事業では酒蔵や醤油蔵のようなクラフト産業を支える物流の仕組みを作ることもできると思っていますし、不動産事業でもまちのハブになるような使い方を模索しています。
2026年からの3年間で、その土台をつくっていこうと思っています。
10年、20年先を見据えた地域への貢献の形は?
人口が減っていくなかで、1事業者の責任はますます大きくなります。自分たちがどんな役割を担うことができるかを常に考え続けたいです。
個人としては、“まちで一番楽しんでいる大人”でありたい。その姿を見せることで、若い人に“倉敷にもこんな大人がいるんだ”と思ってもらえたら嬉しいですね。
個人としては、“まちで一番楽しんでいる大人”でありたい。その姿を見せることで、若い人に“倉敷にもこんな大人がいるんだ”と思ってもらえたら嬉しいですね。

若い世代へのメッセージ
起業や家業承継を考える若者に向けてメッセージをお願いします。
最近、若い人から学ぶことが本当に多いと感じています。だからこそ、触れ合う機会をとても大事にしているんです。一緒に夢を描けるなら、力を貸してほしいし、私も全力で応えたいと常に思っています。
若い起業家や挑戦をしようとしている方は表面的にはとてもキラキラして見えますが、裏側では資金繰りや組織の課題に向き合っていて、とても誠実に活動されている方ばかりだと感じています。私も一緒に挑戦し、未来を描いていけたらと思っています。
若い起業家や挑戦をしようとしている方は表面的にはとてもキラキラして見えますが、裏側では資金繰りや組織の課題に向き合っていて、とても誠実に活動されている方ばかりだと感じています。私も一緒に挑戦し、未来を描いていけたらと思っています。