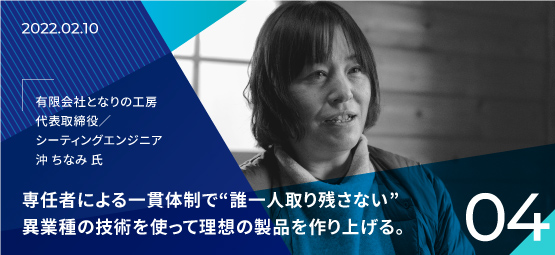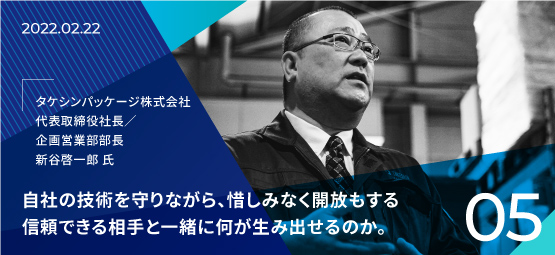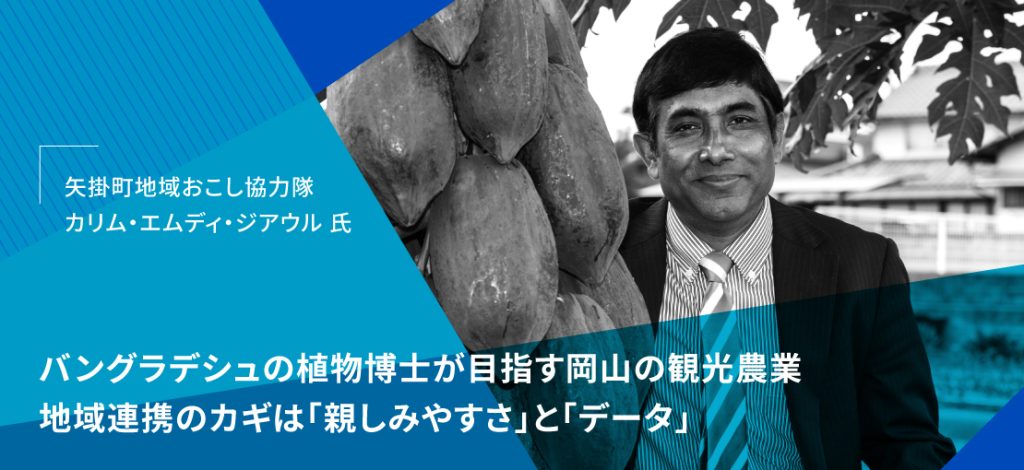INTRODUCTION
of corporate cases and initiatives
PICK UP 取り組み事例紹介
一般社団法人 岡山県地域おこし
協力隊ネットワーク 代表理事
藤井 裕也 氏
協力隊ネットワーク 代表理事
藤井 裕也 氏
PROFILE
岡山市出身。学生時代は考古学を専攻し、ネパールに幾度となく足を運ぶなかで、「日本の田舎を世界から憧れる地域にしたい」という想いを持つ。2011年に美作市地域おこし協力隊に着任。上山地区の棚田再生、梶並集落の地域づくりを経て、協力隊卒業後に、引きこもりの自立支援と移住促進を行う「山村エンタープライズ」を設立。その後は協力隊制度専門家として活躍し、地域おこし協力隊サポートデスクアドバイザー及び、全国地域おこし協力隊ネットワーク企画チーフとして、日本全国の協力隊員や自治体に支援を行う。岡山県地域おこし協力隊ネットワーク代表としても動く傍ら、起業家として様々な事業の立ち上げも行っている。
YUYA FUJII
過疎地域から日本を元気に!
無限の可能性を秘めた地域おこしのカギとは何か。
無限の可能性を秘めた地域おこしのカギとは何か。
現在の活動の基盤を作った、地域おこし協力隊時代
藤井様の現在の取り組みについて教えてください。
岡山県地域おこし協力隊ネットワークの代表として、県内の隊員と自治体の両方を支援する事業を行っています。
また2016年から2024年まで、総務省地域おこし協力隊サポートデスクの専門相談員チーフとして、全国の隊員から相談を受けていました。その経験を基に、現在は全国地域おこし協力隊ネットワークの企画チーフとして活動中です。たとえば、自治体や隊員が持っているノウハウを共有できるような、プラットフォームづくりなどに力を入れています。
他にも、海外のおもちゃの遊び場を提供する「あそびとおもちゃの研究所 あーとあーと」や、高梁川流域の旬の特産品を味わえるインバウンド向け事業「立ち飲み処カケハシ」など、事業家としても活動中です。
また2016年から2024年まで、総務省地域おこし協力隊サポートデスクの専門相談員チーフとして、全国の隊員から相談を受けていました。その経験を基に、現在は全国地域おこし協力隊ネットワークの企画チーフとして活動中です。たとえば、自治体や隊員が持っているノウハウを共有できるような、プラットフォームづくりなどに力を入れています。
他にも、海外のおもちゃの遊び場を提供する「あそびとおもちゃの研究所 あーとあーと」や、高梁川流域の旬の特産品を味わえるインバウンド向け事業「立ち飲み処カケハシ」など、事業家としても活動中です。
現在も様々な形で地域活性に取り組まれていますが、そもそもなぜ地域おこしに興味を持たれたのですか?
私は大学院在学中に、NPO法人だっぴの活動に携わっていました。その中で、多種多様な働き方をしている人たちと知り合い、地域おこし協力隊ともそこで出会いました。
協力隊から、美作市上山地区では、棚田再生のために大規模な草刈りが行われていることを教えてもらい、「地元の人たちと同じ目標を持って、なにかを一緒に取り組めるのが面白そう」と思ったのが最初のきっかけです。田舎で暮らす生き方にも憧れていたし、美作市には魅力的な人も多かったし、田舎を発展させるモデルを作ってみたい……。いろんな想いを持って2011年に美作市の地域おこし協力隊になりました。そこから地域おこしの道がスタートしましたね。
協力隊から、美作市上山地区では、棚田再生のために大規模な草刈りが行われていることを教えてもらい、「地元の人たちと同じ目標を持って、なにかを一緒に取り組めるのが面白そう」と思ったのが最初のきっかけです。田舎で暮らす生き方にも憧れていたし、美作市には魅力的な人も多かったし、田舎を発展させるモデルを作ってみたい……。いろんな想いを持って2011年に美作市の地域おこし協力隊になりました。そこから地域おこしの道がスタートしましたね。
美作市地域おこし協力隊の活動ではどのような取り組みをおこないましたか?また、現在にもつながった活動はありますか?
最初の赴任先だった上山地区では、ひたすら地域の基礎について学びました。地域の人たちが大切にしているマインドや、苦労していること。昔の人が繋いでくれた歴史のこと。「まずは住民と同じ目線にならないと何も始まらない」と思ったので、地域の人との交流を欠かさずに、汗をかきながら必死に覚えました。
2年目からは、過疎化が深刻だった梶並集落が活動拠点となり、「山村シェアハウス」を立ち上げて、県外から起業家を呼ぶ移住促進に挑戦しました。ですが、予想以上に引きこもりの若者の利用者が増えてきたので、それならばと引きこもりの自立支援と移住促進を組み合わせた「山村エンタープライズ」という人おこし事業として再スタートしたんです。思い返してみれば、これがOENの前身となる事業だったと思います。
協力隊卒業後は、私は美作市での経験を全国に広げていきたかったので、さらにキャリアを伸ばす方向へと進み、協力隊支援の場を広げていきました。
当時は、定住しないと地元の人を裏切ってしまうような空気もあったのですが、山村エンタープライズを他の人に受け継いで地域に残したことで、恩返しのひとつとして地域貢献できたのかなと思います。
2年目からは、過疎化が深刻だった梶並集落が活動拠点となり、「山村シェアハウス」を立ち上げて、県外から起業家を呼ぶ移住促進に挑戦しました。ですが、予想以上に引きこもりの若者の利用者が増えてきたので、それならばと引きこもりの自立支援と移住促進を組み合わせた「山村エンタープライズ」という人おこし事業として再スタートしたんです。思い返してみれば、これがOENの前身となる事業だったと思います。
協力隊卒業後は、私は美作市での経験を全国に広げていきたかったので、さらにキャリアを伸ばす方向へと進み、協力隊支援の場を広げていきました。
当時は、定住しないと地元の人を裏切ってしまうような空気もあったのですが、山村エンタープライズを他の人に受け継いで地域に残したことで、恩返しのひとつとして地域貢献できたのかなと思います。

地域の課題は全国共通。解決のヒントは果たしてあるのか
地域おこし協力隊のネットワークを中心に、多くの地域課題が藤井様のもとへ届いていると思います。その中で、特にどのような課題が多くあると感じられますか?
色々とありますが、一番は地域の人たちが自信を持てていないことです。たとえ地域の資源やお金が少なくても、地域の人たちに自信さえあれば、どんな環境でも活性化のチャンスは眠っていると思います。
ただ、地域によっては、既にまちづくりに全力を尽くしてきたところもあると思います。どんなに頑張っても衰退していく現実を見ていたら、モチベーションを保つのは難しいですよね。
ただ、地域によっては、既にまちづくりに全力を尽くしてきたところもあると思います。どんなに頑張っても衰退していく現実を見ていたら、モチベーションを保つのは難しいですよね。
藤井様が考えられる課題解決のヒントはありますか?
なによりも大事なのは、地域の人たちが小さなことから成功体験を積んで、自信をつけること。そして、地域で人同士のネットワークを作ることだと思います。
事業を起こすにしても、イベントをやるにしても、人との関係性が強固であればあるほどできることは増えてきて、やがて自分たちの地域に対する自信がどんどんついてくるんです。
まちづくりの基本は、人と人との関係性の基盤をしっかりと作ること。ネットワークの重要性は、災害時にも活きてくると思います。
事業を起こすにしても、イベントをやるにしても、人との関係性が強固であればあるほどできることは増えてきて、やがて自分たちの地域に対する自信がどんどんついてくるんです。
まちづくりの基本は、人と人との関係性の基盤をしっかりと作ること。ネットワークの重要性は、災害時にも活きてくると思います。
ちなみに、藤井様が新たな取り組みをスタートさせる時に、周囲から理解を得たり、信頼関係を築いたりするためのコツなどはありますか?
私が何かをやる時は、相手に「この取り組みがいかに世の中にとって意義のあることなのか」を、熱意を持って伝えていました。そして、ひとりだけではできないことが多いので、「参加したい!」と思ってもらえるようなプロジェクトにきちんと仕立てることがポイントです。自分がやりたいことではなく、みんなが「これいいね」と思えるような内容にすることが、協力してくれる人を増やすコツだと思います。

必要とされているものを生み出し、日本の地域を元気にしていく
藤井様は地域おこしへの挑戦を続けていますが、その動機ややりがいはどのようなところにありますか?
日本全体で抱えている大きな課題が「人口減少」で、それを解決するには過疎地域の活性化が欠かせないと考えています。利益を得るためにやるのではなく、地域がより良くなるために必要なことだからやっている、という感覚に近いですね。
地域づくりの主役はあくまでも住民や行政で、私ではありません。例えば、地域の特産品を販売するにしても、その地域の人たちだけで、利益を回せるような仕組み作りをすることが重要です。地域が元気になれば、きっと日本全体も明るくなるはず。そのような想いがモチベーションにも繋がっています。
地域づくりの主役はあくまでも住民や行政で、私ではありません。例えば、地域の特産品を販売するにしても、その地域の人たちだけで、利益を回せるような仕組み作りをすることが重要です。地域が元気になれば、きっと日本全体も明るくなるはず。そのような想いがモチベーションにも繋がっています。
今後、藤井様自身が新たに挑戦してみたいことは何かありますか?
地域・行政・協力隊のそれぞれの分野で3つあります。
まず地域でやりたいことは、過疎地域でシェアリングエコノミーの事業を展開することです。シェアリングエコノミーは、個人の持つスキルや資産を流通させる経済モデルで、代表的なものだとメルカリやUber Eatsなどがあります。具体的な内容は模索中ですが、過疎地域には新たなコミュニティの在り方が必要になってくると思います。過疎地域の資産を共有しあって、内部で経済が回せるような新しい仕組み作りをしていきたいです。
行政に向けては、人材育成に力を入れたいですね。大きな目標だと、公(おおやけ)を担う人材育成の学校を作ることです。「貰ったお金を使って、どうやって住民の満足度を上げて、持続可能な地域にしていけるか」そういう意識を持った職員を増やしていけたら良いなと思っています。また、職員ひとりが頑張るのでは意味がないので、組織体制をより良くするための事業も研究中です。
協力隊に関しては、これまで培ってきた協力隊ネットワークを活かして、災害を見据えた「全国ネットワーク組織間の連携体制づくり」を計画しています。
令和6年能登半島地震で、私も実際に被災地へ行き、石川県の協力隊員や協力隊OBの支援をおこないました。そこで、被災しているのにもかかわらず、行政と地域の間に入って色々と動く協力隊員の姿を見て、胸を動かされましたね。
今後は南海トラフ地震も危惧されるので、災害時に必要な金銭的な支援と人的支援を行うための仕組み作りを企画中です。防災面で支援し合える日本全国のネットワークを強化していきます。
まず地域でやりたいことは、過疎地域でシェアリングエコノミーの事業を展開することです。シェアリングエコノミーは、個人の持つスキルや資産を流通させる経済モデルで、代表的なものだとメルカリやUber Eatsなどがあります。具体的な内容は模索中ですが、過疎地域には新たなコミュニティの在り方が必要になってくると思います。過疎地域の資産を共有しあって、内部で経済が回せるような新しい仕組み作りをしていきたいです。
行政に向けては、人材育成に力を入れたいですね。大きな目標だと、公(おおやけ)を担う人材育成の学校を作ることです。「貰ったお金を使って、どうやって住民の満足度を上げて、持続可能な地域にしていけるか」そういう意識を持った職員を増やしていけたら良いなと思っています。また、職員ひとりが頑張るのでは意味がないので、組織体制をより良くするための事業も研究中です。
協力隊に関しては、これまで培ってきた協力隊ネットワークを活かして、災害を見据えた「全国ネットワーク組織間の連携体制づくり」を計画しています。
令和6年能登半島地震で、私も実際に被災地へ行き、石川県の協力隊員や協力隊OBの支援をおこないました。そこで、被災しているのにもかかわらず、行政と地域の間に入って色々と動く協力隊員の姿を見て、胸を動かされましたね。
今後は南海トラフ地震も危惧されるので、災害時に必要な金銭的な支援と人的支援を行うための仕組み作りを企画中です。防災面で支援し合える日本全国のネットワークを強化していきます。
最後に、高梁川流域で新たなことに挑戦しようと考えている方々にメッセージをお願いします
偉人のマハトマ・ガンジーが残した言葉に「あなたがこの世で見たいと願う変化に、あなた自身がなりなさい(You must be the change you want to see in the world.)」という名言があります。「こうなったら世の中がもっと良くなる」と思うものがもしあるなら、まずは自分が動いて、それになれるように頑張ってみてください。私も、まず自分が動くということを意識してこれからも地域おこしに励んでいきます。