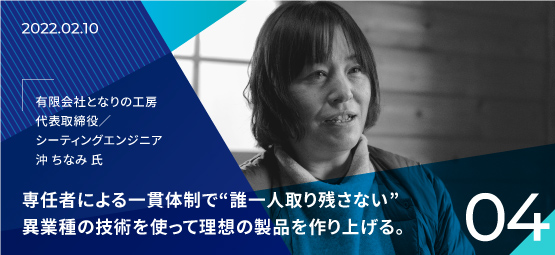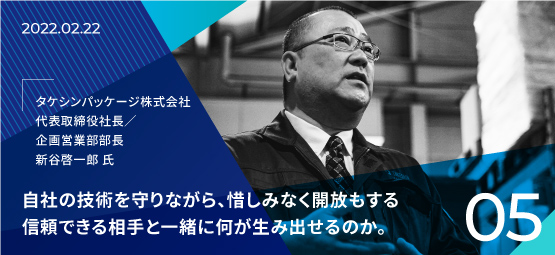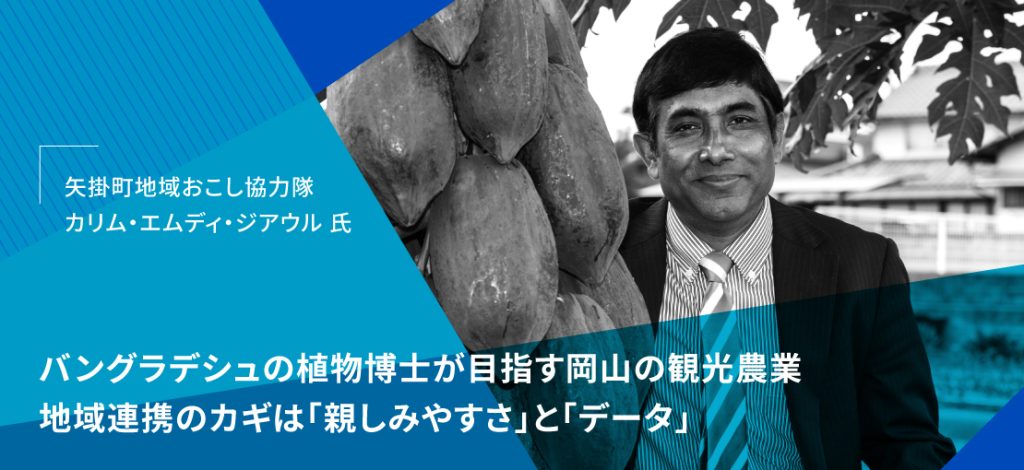INTRODUCTION
of corporate cases and initiatives
PICK UP 取り組み事例紹介
株式会社クラビズ
代表取締役社長
秋葉 優一 氏
秋葉 優一 氏
PROFILE
1972年に創業した地域密着型の広告会社。WEBサイト制作、オリジナルブランド開発・販売、ブランディング・マーケティング支援、飲食、アートなどの幅広い事業を展開する。高梁川流域クロッシングの旗振り役として、サイト運営からフォーラムの企画・開催までを担い、地域の可能性を発信中。「面白そうなことはやってみよう!」という柔軟な社風で、今なお様々な新規事業を立ち上げ、地元倉敷を盛り上げるチャレンジを続ける。
インタビュアー・ライター:杉原未来
カメラマン:難波航太
カメラマン:難波航太
YOUICHI AKIBA
「手の届く場所から未来を変える」 をパーパスに!
社員も地域も世界も巻き込んで、ワクワクできる倉敷をつくる。
社員も地域も世界も巻き込んで、ワクワクできる倉敷をつくる。
「身近な場所」 「身近な人」 への想いが事業の根幹を担う
WEB事業、マーケティング事業から飲食事業まで、幅広い分野で活躍する御社ですが、事業展開の軸はなんでしょうか?
ほとんどすべての事業に共通する軸は「地域の課題解決」です。「人手不足を解消したい」、「売上を増やしたい」など、地域企業の課題と対峙した際に、解決手段をしぼらないことが弊社の強みだと考えています。チラシ作成、ポスティング、WEB制作・運営などは、あくまでもソリューションのひとつ。広告、デザインを主軸にした多様な提案と、ニーズに応えられる可能性そのものが課題解決に対するアプローチなんです。
また、弊社は広告やデザインだけでなく、ものづくり事業にも取り組んでいます。例えば、シルクやウールなど天然素材にこだわった靴下・肌着ブランド「くらしきぬ」は、女性の手足や腹部の冷えからくる体調不良を解決したいという想いから考案されました。販売当初の2012年には、妻、社員、地域の女性など身近な人の健康な姿を思い浮かべ、「この事業に注力したい」と感じたことを覚えています。弊社でブランディング・マーケティングから、ECサイト作成・運営までを一貫しておこない、心も体も温まる商品を全国へ届けています。
さらに、最近ではバスグッズブランド「tatoubi(たとうび)」をリリースしました。マイクロプラスチックが排出されないバスソルトや石鹸を取り扱っています。人の体はピカピカになっている一方で、海はどんどん汚れているっておかしな話だと思うでしょ?瀬戸内海に愛着があるからこそ、お風呂と海はつながっているというメッセージを形にしました。短期的な利益よりも、長期的な利益が大切だと、たくさんの人に感じてほしいですね。会社の経営も、地域課題の解決も同様に、長期的な視点が重要だと考えています。
加えて、飲食店やアート、DJやダンスのイベントも手がけていますよ。未来を担う若者たちが気軽に世界と繋がれる場所を作りたいと考えたからです。思い出がその土地にあれば、気が向いた時に帰ってくるかもしれない。はたまた、倉敷を気に入って移住・定住するかもしれない。お金儲けというよりも、地域活性化につながる仕掛けづくりをイメージして事業を展開していますね。
また、弊社は広告やデザインだけでなく、ものづくり事業にも取り組んでいます。例えば、シルクやウールなど天然素材にこだわった靴下・肌着ブランド「くらしきぬ」は、女性の手足や腹部の冷えからくる体調不良を解決したいという想いから考案されました。販売当初の2012年には、妻、社員、地域の女性など身近な人の健康な姿を思い浮かべ、「この事業に注力したい」と感じたことを覚えています。弊社でブランディング・マーケティングから、ECサイト作成・運営までを一貫しておこない、心も体も温まる商品を全国へ届けています。
さらに、最近ではバスグッズブランド「tatoubi(たとうび)」をリリースしました。マイクロプラスチックが排出されないバスソルトや石鹸を取り扱っています。人の体はピカピカになっている一方で、海はどんどん汚れているっておかしな話だと思うでしょ?瀬戸内海に愛着があるからこそ、お風呂と海はつながっているというメッセージを形にしました。短期的な利益よりも、長期的な利益が大切だと、たくさんの人に感じてほしいですね。会社の経営も、地域課題の解決も同様に、長期的な視点が重要だと考えています。
加えて、飲食店やアート、DJやダンスのイベントも手がけていますよ。未来を担う若者たちが気軽に世界と繋がれる場所を作りたいと考えたからです。思い出がその土地にあれば、気が向いた時に帰ってくるかもしれない。はたまた、倉敷を気に入って移住・定住するかもしれない。お金儲けというよりも、地域活性化につながる仕掛けづくりをイメージして事業を展開していますね。
多様な事業展開の中で、2020年には株式会社KOMA(コマ)を立ち上げたとのこと。そこには、どんな想いが?
倉敷には革新を担当する役が必要だと考え、「街づくり会社」と銘打って株式会社KOMAを立ち上げました。古い文化は、守るものではあるが、すがるものではありませんからね。街の人々が学びに触れる機会を創出する「学び事業」、アートやスポーツを通じて多様性のある街づくりに貢献する「カルチャー事業」、起業家育成や事業承継サポートなどをおこなう「企業支援事業」など、地域に刺激を与えられる事業を展開しています。
私の尊敬する人物は、チェゲバラ、白洲次郎、そして倉敷の街をつくった大原孫三郎の3人。常識を打ち壊して新しいことにトライする人が好きですし、自分もそうありたいと思っています。なかでも、大原孫三郎は、銀行をつくり、美術館をつくり、脈々と革新をつないできました。倉敷には、大原家のもつパイオニア精神が根付いています。これに触発されて、株式会社KOMAを立ち上げたんです。
私の尊敬する人物は、チェゲバラ、白洲次郎、そして倉敷の街をつくった大原孫三郎の3人。常識を打ち壊して新しいことにトライする人が好きですし、自分もそうありたいと思っています。なかでも、大原孫三郎は、銀行をつくり、美術館をつくり、脈々と革新をつないできました。倉敷には、大原家のもつパイオニア精神が根付いています。これに触発されて、株式会社KOMAを立ち上げたんです。

「新しい産業を生み出す」 いう意気込みでのぞむ高梁川流域クロッシング
熱意をもって街と向き合う秋葉さんですが、高梁川流域クロッシングの旗振り役となるモチベーションはどこからくるのでしょう?
危機感がモチベーションになっているのかもしれません。倉敷市は、雇用があり、観光資源があり、行政サービスも豊かで、本当に恵まれた場所ですが、その一方で、危機感が醸成されない地域であることも確かです。今は暮らしやすい街ですが、10年後は同じ状況では無いと思います。例えば、大きな企業が倉敷から出ていったらどうしますか?新しい成長産業を今のうちに作っていないと、危ないのではないかと思いませんか?周囲がなかなか重い腰をあげないのだったら、自分が苦しい思いをしてでも新しい産業を作ろうと考えました。「ここからイノベーションのきっかけを生み出すんだ」という気持ちを込めて、高梁川流域クロッシングに取り組んでいます。嫌われようと、笑われようと、やってやろうという意気込みでね。
高梁川流域クロッシングのキーワードは「オープンイノベーション」です。この開かれた観念を、若い人たちでさらに広げてほしいと思っています。2022年のパネルディスカッションにご登壇いただいた日本共創プラットフォーム社長(当時)の冨山和彦さんも、2025年にご講演をいただいた宮田さんも、同様の意見をお持ちでした。私たちができるのは、ビジネスの化学反応が起こる環境の整備。僕なんて、今のうちから第一線を退くための準備を始めようかと考えています。
高梁川流域クロッシングのキーワードは「オープンイノベーション」です。この開かれた観念を、若い人たちでさらに広げてほしいと思っています。2022年のパネルディスカッションにご登壇いただいた日本共創プラットフォーム社長(当時)の冨山和彦さんも、2025年にご講演をいただいた宮田さんも、同様の意見をお持ちでした。私たちができるのは、ビジネスの化学反応が起こる環境の整備。僕なんて、今のうちから第一線を退くための準備を始めようかと考えています。
高梁川流域クロッシングに4年間携わって得た、気づきを教えてください。
気づきはたくさんありましたね。まず、最初の2年間はスタートアップ創出のため奮闘しましたが、それは難しいことに気がつきました。倉敷市には大きな大学が複数あるわけでもなく、スタートアップ支援の立役者がいないんです。俗にいう、キラキラスタートアップは生まれないと気づき、倉敷の持つポテンシャルについて改めて考えたところ、医療分野に注目する運びとなりました。
実は倉敷市、「予防医療の街」なんです。そもそも日本ほど医療費がかかっている国は他にありません。健康保険制度も充実しており、多くの方が気軽に病院へ行ける仕組みがあります。だからこそ、罹患する前の予防医療にまで意識が及んでいるのです。2025年の高梁川流域クロッシングフォーラムは倉敷中央病院付属予防医療プラザで開催しました。他業種分野と予防医療分野のクロッシングには可能性があると感じています。
実は倉敷市、「予防医療の街」なんです。そもそも日本ほど医療費がかかっている国は他にありません。健康保険制度も充実しており、多くの方が気軽に病院へ行ける仕組みがあります。だからこそ、罹患する前の予防医療にまで意識が及んでいるのです。2025年の高梁川流域クロッシングフォーラムは倉敷中央病院付属予防医療プラザで開催しました。他業種分野と予防医療分野のクロッシングには可能性があると感じています。

高梁川流域クロッシングに込めた想い、「倉敷ならできる!」
最後に、倉敷市に関係する多くのステークホルダーの方々へメッセージをお願いします。
解体新書、地動説、相対性理論、その当時多くの人が批判していたものが現在の当たり前になっています。先入観や常識にとらわれない考えから生まれる変革が社会をリードしてきました。これから何かに挑戦しようと考えている方は、是非とも常識を壊すところからはじめていただきたいですね。
大原孫三郎も、街に変革を起こした挑戦者の一人。事業家のために銀行をつくり、労働者のために病院をつくり、一般人のために美術館をつくりました。倉敷は「オープンイノベーション」や「SDGs」という言葉もない時代に、様々な革新が生まれたすごい街です。今後も「倉敷ならできる!」という思いを胸に、倉敷市をイノベーターが集まる街にしたいですね。
大原孫三郎も、街に変革を起こした挑戦者の一人。事業家のために銀行をつくり、労働者のために病院をつくり、一般人のために美術館をつくりました。倉敷は「オープンイノベーション」や「SDGs」という言葉もない時代に、様々な革新が生まれたすごい街です。今後も「倉敷ならできる!」という思いを胸に、倉敷市をイノベーターが集まる街にしたいですね。