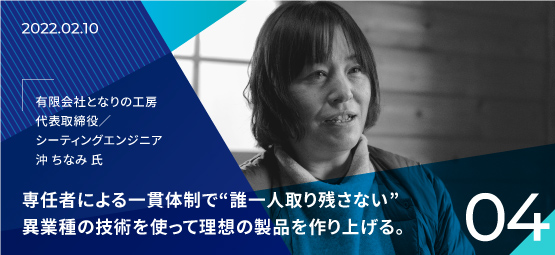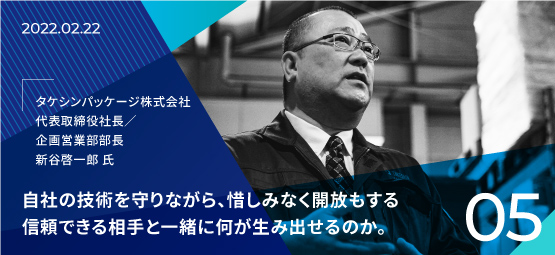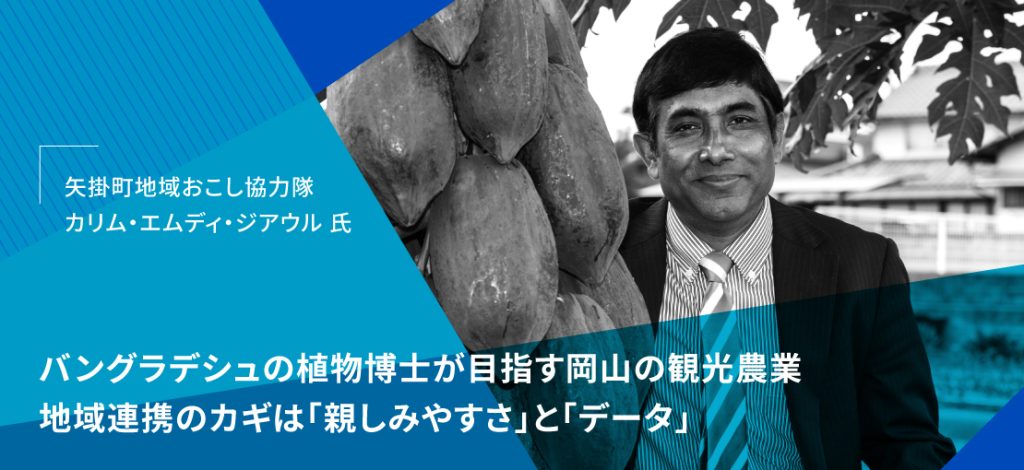INTRODUCTION
of corporate cases and initiatives
PICK UP 取り組み事例紹介
中小企業基盤整備機構
創業・ベンチャー支援部長
石井 芳明 氏
石井 芳明 氏
PROFILE
1987年岡山大学法学部法学科卒業後、通商産業省(現・経済産業省)に入省。中小企業・ベンチャー企業政策、産業技術政策、地域振興政策等に従事する。その間も、カリフォルニア大学バークレー校に留学、青山学院大学大学院にて修士課程、早稲田大学大学院にて博士課程を修める。2012年から経済産業政策局新規産業室の新規事業調整官、2018年に内閣府に出向、2021年から経済産業省新規事業創造推進室長、2024年から現職。
YOSHIAKI ISHII
地方スタートアップに必要な
「協力」 と 「教育」 を目指して、今こそReunionを。
「協力」 と 「教育」 を目指して、今こそReunionを。
スタートアップに対する想い
経産省での活躍のみならず、地域経済や新規事業についての著書も数多く残されている石井さん。近年国が注力しているスタートアップ支援の大きな流れを簡単に教えてください。
スタートアップ支援は2013年に始まりました。安倍政権の掲げた「三本の矢」の一つである成長戦略にベンチャー企業支援が含まれていたのです。2022年には、岸田政権の掲げた「新しい資本主義」が開始。経済成長と社会課題解決に対して同時に取り組む企業が求められるようになりました。しかし、既存企業ではなかなか社会課題解決まで達しないため、新しい企業を生み出す流れが始まったのです。スタートアップを生み育てるエコシステムを創出するため「スタートアップ育成5か年計画」ができました。そこでは、「スタートアップ創出に向けた人材・ネットワークの構築」「スタートアップのための資金供給の強化と出口戦略の多様化」「オープンイノベーションの推進」という3本柱の取り組みを推進していくことに。主導は経産省ですが、「スタートアップ創出には他省庁の抱える行政課題・地域課題を解決できる糸口がある」と、総務省や文科省など他省庁との連携を図りました。石破政権では、「地方創生」の切り口でスタートアップに注目が集まっています。現在では、地域の「ゼブラ企業」や「後継ぎベンチャー」が存在感を増していますね。国や地域大学にもスタートアップに関する研究成果やデータが集積しはじめました。スタートアップを取り巻く大きな流れは、「さあ、これからいいスタートアップが出てくるぞ」というフェーズに入っています。
良い流れができているなかで生まれた地方スタートアップの勝ち筋や可能性、そして、浮かび上がった課題について教えてください。
地域経済界のリーダーたちと、スタートアップ企業との協力が地方の勝ち筋だと考えています。例としては、岡山でも2023年に開催された「BLAST SETOUCHI(ブラスト セトウチ)」が挙げられます。これは瀬戸内エリア最大級のスタートアップイベントで、ナカシマプロペラさん、両備グループさんなど地域の中核を担う企業が参加されていました。そこで、スタートアップをリスペクトする交流の場が重要だと、改めて感じました。他にも欠かせないものは「ファイナンス」です。特にスタートアップは時代の先駆けとなるような新事業が多く、時間が勝負ですから、リソースが足りないと瞬発力に懸けてしまいます。課題は「エクイティファイナンスをどうやって準備するのか?」という点です。地域の資源をスタートアップに供給するのか、あるいはエンジェル投資家の力を借りるのか。とにかく、返済期限の定めがない「息の長いお金」がスタートアップには必要です。地銀には、「地域企業がベンチャーデットを使えるような仕組みの整備」が求められるでしょう。地域経済界のリーダーや、地域経済の中核である地銀が、スタートアップを見守ることで、課題解決に向かっていけるはずです。岡山は課題解決に必要なキープレイヤーが揃っていると感じています。

倉敷・高梁川流域でのスタートアップ・イノベーションの可能性
倉敷市・高梁川流域という地域性のポテンシャルをどう感じていらっしゃいますか?
倉敷市・高梁川流域には繊維産業をはじめとして、水島コンビナート、総社の自動車産業、高梁市のベンガラなど特徴ある地域産業がありました。それらの産業は一度ピークアウトしているものの、繊維産業は今でも「日本代表」です。現在、紡績工場はなくなりましたが、デニム加工という新しい産業が芽を出しています。古い産業の存在は諸刃の剣とも言えます。新しい産業が入りにくい可能性があるからです。しかし、産業の基礎知識があり、イノベーションが生まれやすいというアドバンテージもあります。産業のポテンシャルはとても高いので、工夫次第でレベルの高いイノベーターが誕生するかもしれません。
故郷への想い入れはありますか?
やはり岡山は特別な場所です。大学を歩いていても懐かしさを感じますね。気候も良いし、産業もあるし、特産品も多く、世に対して誇れる場所だと思っています。私の他にも「岡山でスタートアップやイノベーションがあるなら応援したい」という人は沢山いるのではないでしょうか。複数大学が合同開催したピッチコンテストや高梁川流域クロッシングフォーラムなどの場を介して、全国のイノベーターや岡山出身の著名人に集まってもらえており、これは大きな成果だと感じます。
地方自治体から民間への支援として期待することは何でしょうか?
地方自治体の企画する「起業家教育」に期待しています。起業家教育では、自ら問いを見つけ、問いを発する力を育てます。起業家精神を養うなかでは、輝く人も失敗する人も出てくるでしょう。しかし、起業だけが成功ではありません。起業に失敗する人、起業家をフォローする人、後からプロジェクトに参加する人、多様な人が居ていいと思います。スタンフォード大学心理学教授キャロル・ドゥエック氏は、「失敗は進歩の過程である」と表現しているほどです。ただし、失敗が致命傷にならないようにだけ気をつけていただきたい。失敗が小さなうちに撤退するという「撤退ルール」を頭の隅に用意しておくことが起業家教育の一つかもしれません。小さい頃、転びながら自転車に乗る練習をしましたが、大人になって思い切り転んだら大怪我をします。地域で行う起業家教育にも、「失敗の訓練」という要素が盛り込まれるといいですね。笑って語れる失敗がある人こそ、挑戦できている人ですから。

地域に求められる「起業家教育」のこれから
学校教育で求められるものは何でしょう?
起業家教育といっても、教育現場に任せるには負担が大きすぎます。そのため、地方自治体や民間企業と、教員や学生がチームを作り、協力して取り組む教育手法が理想的です。また、「地域を活性化したい!」と思ってくれる学生が増えるためには、社会を盛り上げているかっこいい大人との交流が必要です。例えば、一般社団法人インパクトスタートアップ協会では、名だたる経営者を学校へアテンドし、高校生活や起業までの経緯を話してもらうという活動をおこないました。すると、話を聞く高校生たちの目がキラリと輝く瞬間があったのです。学校教育の一環として、卒業生の先輩が活躍している姿を母校で見せられる機会が増えるといいですね。
最後に、これからスタートアップに挑戦していきたいと思っている方々へメッセージをお願いします。
とにかく頑張る、続ける、周囲を巻き込む。スタートアップ支援も地方創生も長く続かないという課題があります。人がいなくなると企画が無くなる、補助金がなくなると活動も終わるというのがよく見られる現実です。この課題にしっかり向き合い、乗り越える若い方が多く現れてほしいと思います。逆説的かもしれないですが、将来地元で起業を考えている若い方は、一旦他県に出て、地域の特色を知ってもらうと起業の際に経験が活きてくるのではないでしょうか。そして、何事も最後は楽しむことを忘れずに!失敗を恐れず、チャレンジしていただきたいですね。